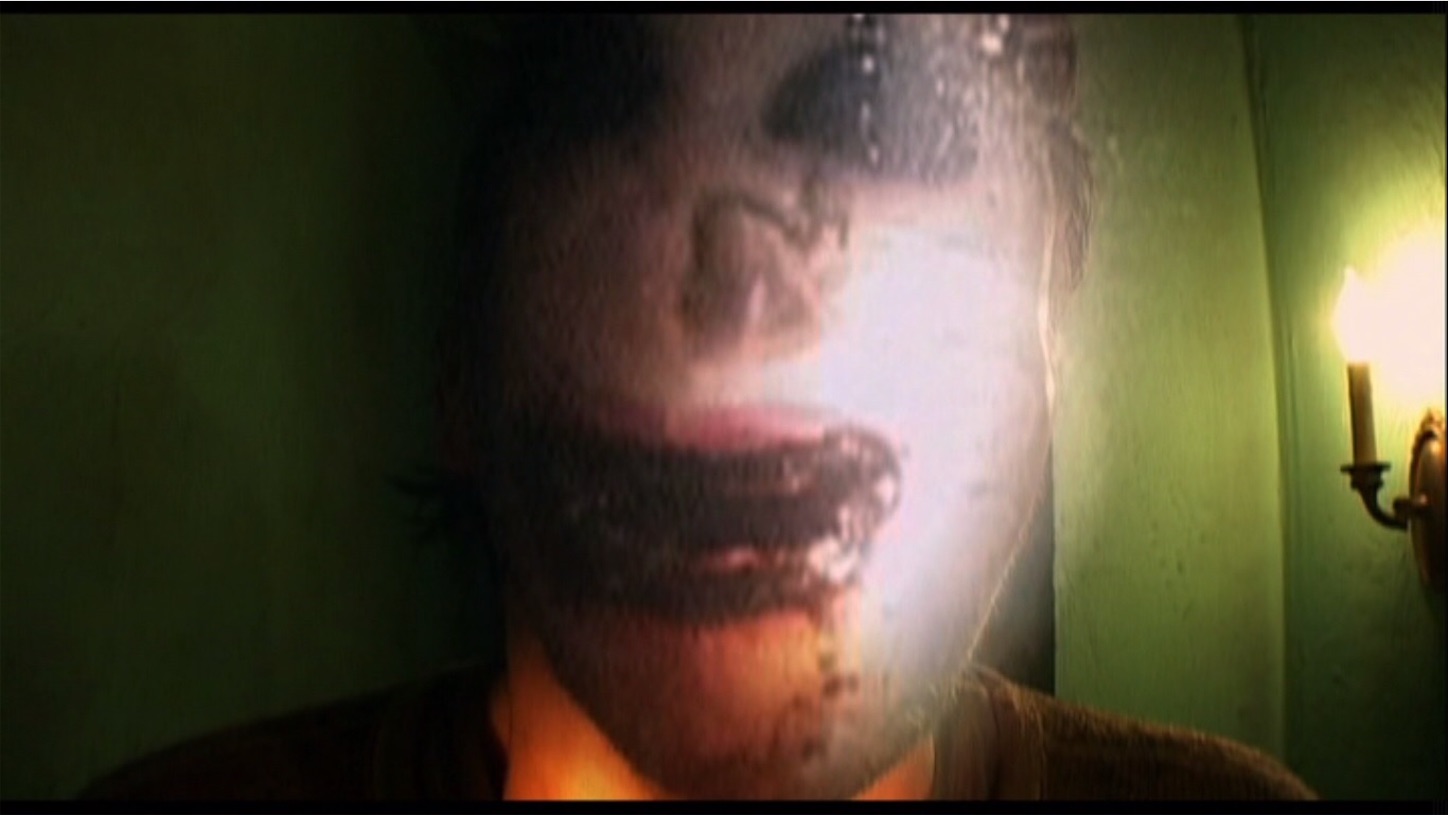ショーン・ベイカー『フロリダ・プロジェクト』

とにかくうまい。驚くほどうまいですね、この映画は。
子供たちのホントにいい絵が撮れているんですね。

ドラ猫ギャング団
ショーン・ベイカーという監督の作品はコレ以外に見たことないんですけども、相当な演出力の持ち主であることが、冒頭のシーンでわかりますね。
まあ、なんともかわいい悪ガキどもでしょうか(笑)。
主人公ムーニーのお母さんは、身体にゴッツい入れ墨を入れている、ロッキンなシングルマザーです。
一見楽しそうなお話しなのですが、よくよく見るとコワイ映画なんですね。
このお母さん(と呼ぶにはなかなか厳しい人ですが)、と娘のムーニーが住んでいるのは、モーテルです。

ムーニーたちの住む、マジック・キャッスル・モーテル
要するに、賃貸住宅に住むことができないほど貧しい人たちなのです。
とんでもない大富豪がいて、史上最強の軍事力を持った国に、こんなに貧しい人々が住んでいるんですね。
そういう厳しいと現実をこの監督は、チラッチラッと見せるんです。
子供たちの視点からは一切そういう厳しい現実には気がつかず、当人たちは楽しくノラ猫ライフを送っているのですが、それがむしろコワイですね。


子どもたちのシーンだけを見ていると、『やかまし村の夏休み』なのだが。
明確なストーリーがしっかりあるお話しではなく、子供の視点から見た現実なので、夏休みをエンジョイしているという事が描かれているんですけども、観光客相手に盗品を売ったり、売春などをしてまともな定職につかない母親、そんな親子の事を可哀想に思う、モーテルの管理人のボビー(なんと、ウィレム・デフォーです)。

ムーニー親子を気遣う、ボビー(ボビー・ペルーではありせんよ)。
ディズニーランドの花火が盛大に打ち上がるのを見て楽しむシーンが出てきますので、モーテルはオーランドのディズニーランドのすぐ近くにあるのがわかるんですけども、あの「夢の国」のすぐ近くにある、ドン底の世界。という強烈な対比を淡々と描いていますね。

ディズニーランドの花火を楽しむ親子。
しかも、主人公の女の子には、その事が全くわからず、毎日が楽しい日々でしかないという。
子どもというのは適応能力が抜群にあって、現実はそういうものだと思うと、そこで楽しみを見つけてしまうので、客観的にはかなりマズイ生活なのですけど、子どもたちと楽しく遊んで、花火を見ていられるので、何の問題も感じてないんですね。

このシーンは見てのお楽しみ(笑)。
しかも、その天真爛漫ぶりが、あまりにも自然に画面に収まっていているのが、見ている私たちの胸に突き刺さってきます。

子ども達に自由にやらせている脇を、ベテランのウィレム・デフォーが、ホントにただの管理人のおっさんを演じる事で(特に大活躍も何もありません)、リアルをちゃんと表現しているところがこの映画のキモであり、陰のMVPは、やはり、デフォーと言えるでしょう。
最近のアメリカ映画は、ハリウッド大作よりも、こうした低予算映画にいいものが増えてきていている気がしますね。必見。