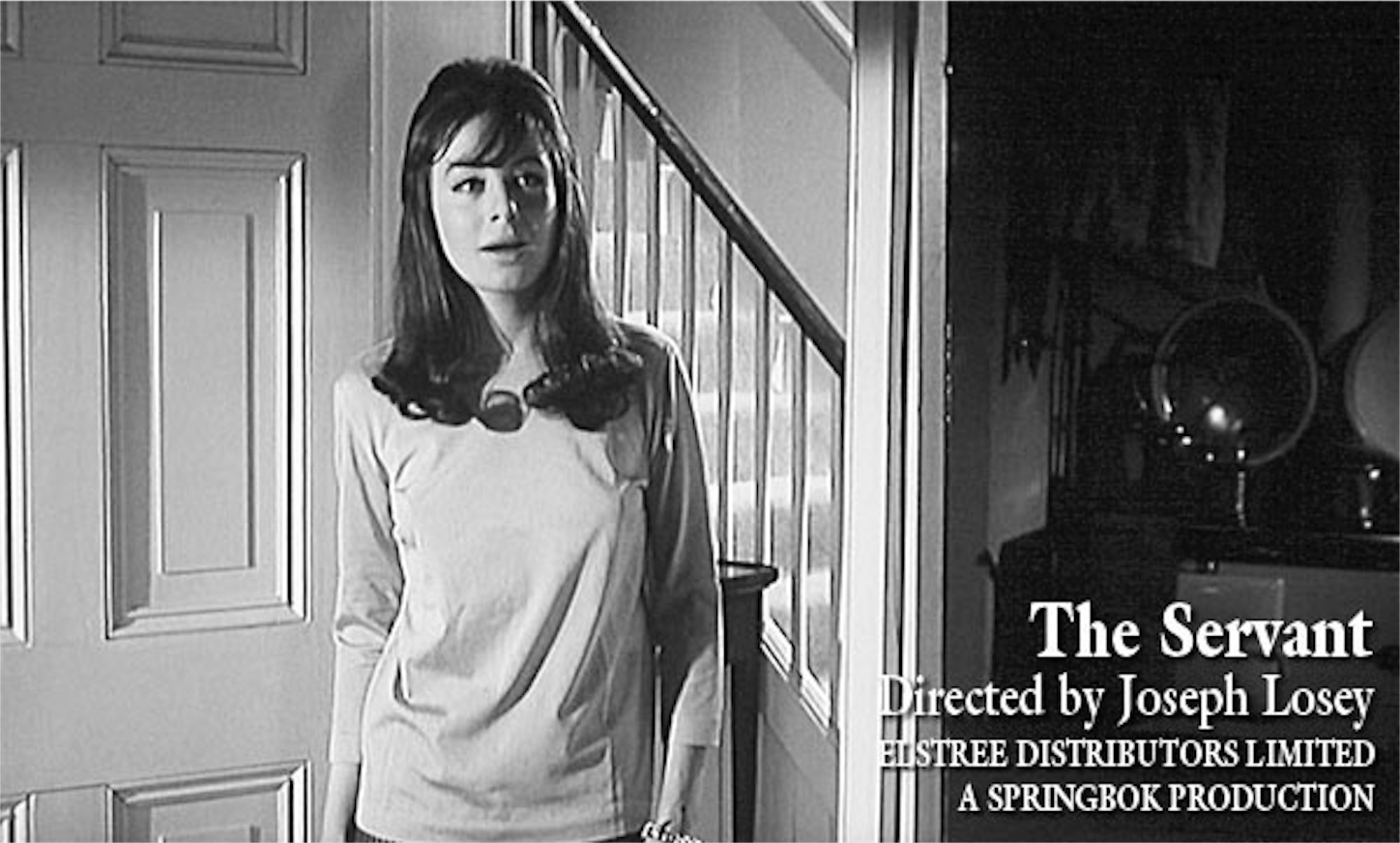ジーン・ケリー、
スタンリー・ドーネン
『雨に唄えば』

これぞ、「見た気になっている映画」の筆頭かもしれません。
舞台がサイレント映画末期のハリウッドである事すらよく知られてないかも。
主人公を演じるジーン・ケリーは旅芸人から、大スターにまで上りつめた、いわば、アメリカン・ドリームを体現した男です。

とにかく、歌いまくり、踊りまくるケリーですが、今見ても唖然とするほどうまい。
圧倒的です。
共演のドン・オコナー、デビー・レイノルズも見事。

3人が意気投合するシーン。
劇中でのケリー主演の映画の剣劇シーンにおけるカラダのキレはホンマもの。
スタントなど要りませんね。
さて、とうとうトーキーの時代がやってきました。
実は、この時代をうまく乗り越えられなかった監督や俳優は結構多いんです。
日本でも阪東妻三郎がかなり低迷したんですが、原因は声でした。
バンツマの地声は甲高かったんですね。
役のイメージとのギャップがかなりあったんです。
コレを無理矢理ドラ声に変えたら人気が回復したんですけども、ケリーの相方の女優も、ルックスは申し分ないのですけども、声がバカっぽいというか(笑)、残念なヴォイスで更にバカっぽくしゃべるという人で。
この役者がしゃべらなくてはならない。という状況は、演技の仕方や演出の仕方など、要するに映画全体に及ぶ大変化なので、サイレント期からキャリアを始めた監督や役者は、スランプになったり、引退してしまう人がいたんですね。
これは、カラー撮影になった事や、70mm画面になった事、デジタル撮影、コンピュータによるポストプロダクションよりも劇的であったと言えます。
これらは、ある意味、採用しなければいい。とは言えます。
カラー撮影はもう基本なので、さすがにもう無視できませんが(黒澤やフェリーニ、ウェルズはなかなかカラーにしませんでした)。
相方のしゃべりにモンダイがある。コレは致命的ですよね。
時代の変化に対応できない。
こんな話だった。ってみなさん知ってました?
あのケリーがどしゃ降りの中で踊っているクラシック映画としか思ってなかったのでは?
トーキーなのだから、歌と踊りをふんだんに入れたら面白い!という、なんともアメリカ的で大らかな発想が、MGMという映画会社に空前の繁栄をもたらしましたが、フレッド・アステアと並ぶMGMの大スターであったジーン・ケリーが、トーキーへの転換期を描き、トーキーの素晴らしさ、カラー撮影の素晴らしさを満天下に知らしめるという、この発想の素晴らしさ。
実際、画面から溢れんばかりの多幸感は、今のハリウッド映画からは失われた世界ですね。
撮影所の中を、長年の相方である伴奏者(撮影する横でピアノを演奏して、役者をいい気分にする仕事なんです。こんな仕事があったんですね)と歩くシーンがいいですよ。

オコナーの素晴らしいシーン
多分、1920年代の終わり頃ってこんな風に映画を撮影してたんですね。
大恐慌前の空前の好景気だったアメリカを懐かしんでいる。という側面も見逃せませんね(「私はカルヴィン・クーリッジよりも稼いでいる!」というセリフが出てきます)。
あと、この作品の振り付けはケリーが全部やっていると思うんですが、アステアと違うのは、アステアはとにかくエレガントでエレガントでもうトコトン洗練された美を追求しているんですけども、ケリーはコミカルでパワフルですね。
顔の表情まで振り付けているんです。
このケリーの振り付けに現在の作家で一番影響受けてるのは、間違いなくジャッキー・チェンです。
ジャッキーは、バスター・キートンの後継者でもありますが、あの顔の面白さと、ベタだけど笑っちゃうセンスは、本作や『パリのアメリカ人』なんかをよく研究していたんじゃないでしょうか。
話が横道にそれましたが、ここから急に史実が入ってきます。
アル・ジョルスンという、顔を黒く塗って黒人に扮装して歌っていたユダヤ系の歌手がいたのですが、彼を主演とした『ジャズ・シンガー』が大ヒットしました。
トーキー第1作です。
ケリーが撮影していた、フランス革命ロマンス(そんなのにばかり主演をしてます)も、トーキー撮影に急遽変更せざるを得なくなりました。
しかし、トーキーでは、共演の女優のあのバカっぽいしゃべりが致命的!!
さあ、どうなるんだ、どうなるんだ。というところまでにしておきましょうか。
ここからがホントに面白いですよ。

この売れない女優さんとの出会いが決定的な事に

そのキャシーのお仕事。いわゆる営業ですね。
「トーキー旋風」を見せるシークエンスがもう今見るとサイケでキッチュで可愛いんですよ!
合成なんかもやっちゃって。
あの『あまちゃん』の重要な伏線の元ネタもココでやってたんですね。
なかなかあのどしゃ降りのシーンが、ここまででは結びつきませんが、そこが見どころなのです!
あの伝説のシーンについては何も言いませんが、アレを現代的に捉え直して大スターになったのは、マイケル・ジャクスンあるという事は言っておきましょう。
ちなみにいうと、アレはラストシーンではありません。
50年代のエンターテイメントが大好きなのでしょう。
80年代を代表する映画と音楽の大スターが、この映画の影響を受けているというのは、恐らくは偶然ではないのでしょう。
私、ミュージカル映画って、どうも苦手でほとんど見てませんが、そういうものを超えたすごさが本作にはあります。
古典がもつ圧倒的な強度です。
映画館でデジタルリマスター版が上映されたら、絶対に観に行きますよ。
この頃のハリウッドは、どう割り引いて見ても黄金期と言わざるを得ませんね。

実はラストシーンではないという事実!
※デビー・レイノルズが2016年にお亡くなりになりした。合掌。